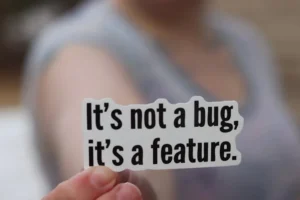お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!
「毎日Excelの転記に3時間を吸われている」「頼れるIT担当が不在で、業務改善が進まない」。私は2024年に支援した販社で、まさに同じ悩みを抱えていた現場に向き合いました。手作業の集計と属人化したマクロ、月初の修正依頼で夜遅くまで残業――この“Excel地獄”をどうやって抜け出したのか。本記事では、現場が抵抗なく動き出す段階的なDX推進術を、PjMの実務と意思決定の視点で解説します。仮説思考 で学んだ「仮説→検証→改善サイクル」の型を、現場改善にどう適用したのかも合わせて紹介します。
「いきなり新システムを導入するのではなく、現場のリアルを把握してから投資判断したい。そうすれば、Excel地獄から抜けられるはずだ。」
この言葉は、私が支援した現場リーダーの振り返りです。Excel依存を断ち切るには、ツール導入前に「今、どこが苦しいのか」「どこから手を付ければ抵抗が少ないか」を見極めることが鍵になります。
非IT部門が抱えるExcel業務の現実と課題
手作業コピペ地獄の実態を可視化する
非IT部門では、メールで届いたExcelをコピー&ペーストし、1枚の集計シートに転記する作業が日常化しています。私が営業企画部門を観察した際、売上集計だけで月40時間の工数を消費していました。さらに、ミスを恐れてダブルチェックを行うため、担当者の疲弊感は極限まで高まります。転記の自動化ステップはPython自動化の書籍で示されるタスク分解の型が役立ちました。
私は、どのセルをどのタイミングで編集しているかを記録し、実際の操作動画も残しました。すると、データ転記と転記後の照合作業に全体の60%が費やされていることが判明。Excelを完全に捨てる前に、「転記と照合の自動化」を最初の改善テーマに据える根拠が整いました。
属人化マクロがブラックボックスになる
ExcelマクロやVBAは即効性の高い改善手段ですが、メンテナンスを怠ると「作者しか触れない魔境」になります。経理部門で見つけた月次決算シートは、1000行のマクロと複雑なネスト関数が混在し、作者以外は触れない状態でした。
私は「マクロの使用ログ」「更新履歴」「バージョン管理状況」をヒアリングし、リスクマトリクスを作成。属人化の度合いが高い箇所をマッピングして、「どの部分はノーコード化」「どこは外部ツールへ移管」といったロードマップ作りにつなげました。
ミスと再作業の悪循環を断つ
人手でのコピペはヒューマンエラーを誘発します。ある人事部門では、転記ミスが毎月2〜3件発生し、確認作業でさらに5日間が捧げられていました。私は失敗ログを収集し、「どの処理でどんなミスが起きたのか」を時系列で整理。ミス率の高い工程から自動化やチェックリスト整備を行い、エラー本数を半減させました。

なぜExcel業務改善が進まないのか
IT部門と現場の認識ギャップ
現場は「少しだけ楽になればいい」と考えていても、IT部門に相談すると「大規模刷新が必要」「費用対効果が合わない」と判断されることが多々あります。私は橋渡し役として、現場の言語とITの言語を翻訳し、段階的な改善計画を作成しました。双方の温度感を合わせることが、プロジェクト成立の第一歩です。改善検討の合間に、全社コミュニケーションの整備方法を解説したAIプロジェクト期待値コントロール術も参考にしました。
こうした温度差を埋めるためのDX推進ロードマップは [book_dx_全社員] でも「現場を巻き込む意思決定プロセス」として詳しく整理されています。
現場の変化抵抗と心理的ハードル
「昔からExcelで何とかなってきた」「新ツールを覚える余裕がない」という声は、どの部門でも聞かれます。私は若手社員をアンバサダーに任命し、彼らにノーコードツールを触ってもらってからベテランへ展開する「リング状の導入プラン」を採用しました。小さな成功を共有することで、現場の納得感が得られます。
予算と投資優先度の壁
経営層にとって、Excel改善は投資優先度が低くなりがちです。私は「現状の時間コスト」「改善による削減効果」「リードタイム短縮」をデータ化し、ROIを算出した上で投資判断を仰ぎました。小さな自動化で成果を出し、翌年度の本格投資へ繋げるストーリーを描くのがポイントです。

PjMが実践する段階的DXアプローチ
Phase1: 現状可視化と課題抽出
最初のステップは、Excel業務の実態を可視化することです。私は業務ヒアリングと操作録画、工数ログの収集、ミス発生率の計測を通じて、どの工程がボトルネックかを見極めました。現状を「見える化」することで、改善余地を論理的に示せます。特に、作業時間のヒートマップとエラー件数のグラフを用意すると、経営層やIT部門にも改善対象が一目瞭然になります。ここで得た示唆は内部共有資料として整え、改善計画の土台にしました。
Phase2: クイックウィン施策の投入
可視化で得た課題を踏まえ、1〜2ヶ月で成果が見えるクイックウィン施策を投入します。ピボットテーブルやPower Queryで転記作業を半自動化したり、簡易マクロで定型処理を自動化したりするだけでも、月数十時間の削減が可能です。この段階で「やれば変わる」という感触を現場に提供します。私は成果を共有する際に、改善前後の動画と削減工数をセットで提示し、メンバーの納得感を高めました。
Phase3: フロー再設計と段階的ロールアウト
クイックウィンで信頼を得たら、ノーコードツールやSaaS導入、さらには業務プロセスの再設計に着手します。私はまず一部門で試験運用し、効果と課題をフィードバック。改善を繰り返した上で全社展開に移ることで、導入時の混乱を抑えました。アジャイルサムライ のレトロスペクティブパターンを参考に、各フェーズでの学びを必ずドキュメント化し、次のフェーズに反映させています。運用面の詳細はAIプロジェクトのPoC墓場を避ける戦略からも学べます。
Excel業務改善の3つの選択肢
短期で効果を出すなら、既存のExcelを活かしながら自動化するアプローチが有効です。私はコードにコメントや更新履歴を残し、引き継ぎ難易度を下げるルールを整備しました。属人化は防ぎながらも、即効性のある改善を実現できます。マクロ化する際は、必要なライブラリや想定入力をシート内に明記し、将来の改修コストを抑えました。
ノーコード/ローコードツール活用
Power Automate や kintone などのノーコードツールは、業務アプリを短期間で構築できます。私は営業部門向けにkintoneを導入し、顧客情報検索時間を90%削減しました。ツール設計は現場主導とし、IT部門はセキュリティとメンテナンスの支援に特化するとスムーズです。
本格システム導入
全社標準化や大規模な業務改革が必要な場合は、ERPやSaaS導入が選択肢になります。私は段階的なPoCと投資判断フレームを用意し、拙速な導入を避けました。リードタイムやコスト削減効果を定量化し、システム導入の妥当性を継続的にモニタリングします。
導入後のノウハウ整理には セカンドブレイン のデジタルノート活用術を採り入れ、改善ログや議事録をいつでも検索できる環境を整えました。

現場を巻き込む推進体制の作り方
キーパーソンを発掘する
改善を進めるには、現場の信頼を得られるキーパーソンの協力が不可欠です。私は業務に精通しつつ改善に前向きな担当者をプロジェクトコアメンバーに迎え、彼らの課題感を優先して解決することで支持を得ました。改善活動に参加するメンバーへは、集中力を支える ロジクール MX KEYS (キーボード) と ロジクール MX Master 3S(マウス) をセットで支給し、物理的な環境からも推進力を後押ししました。
チーム・ジャーニー 併せて、知識共有を定着させるためにObsidianとCursorを組み合わせたナレッジ循環術を活用し、改善ログを誰でも参照できるようにしました。
小さな成功体験を共有する
私は週次で「改善報告タイム」を設け、削減できた時間や業務改善の成果を共有しました。成功体験を可視化すると、他部門からも協力したいという声が届き、改善の輪が自然と広がります。
継続的な改善サイクルを整備する
四半期に一度「業務改善ミーティング」を実施し、現場からの改善提案を募る仕組みを整えました。採用された改善案は表彰制度で称え、改善文化を根付かせています。

よくある失敗パターンと対策
全面刷新による混乱
いきなり全社的な刷新を行うと、現場の抵抗で頓挫するリスクが高まります。私はまず一部門でリプレイスを試し、操作性や補助資料をブラッシュアップしてから横展開することで、障害を最小化しました。
IT主導の押し付け
現場の実態を無視してIT部門がツールを押し付けると、使われない仕組みが量産されます。私はプロジェクト初期に現場ヒアリングを徹底し、導入するツールは現場が選定する方針を徹底しました。あわせて プラットフォーム革命 にあるプラットフォーム思考を共有し、外部パートナーとの役割分担も整理しました。
教育不足による定着失敗
導入後の教育を軽視すると、「ツールは入ったが誰も使わない」状況になります。私は導入後にオンボーディング会を開催し、操作マニュアルと動画コンテンツを用意。ファシリテーション入門 を参考に、参加者の合意形成とフォローアップ質問をスムーズに回す進行台本も用意しました。導入から3ヶ月間は月次のフォローアップセッションを行い、定着率を可視化しています。ナレッジ循環の仕組みはCursorとObsidian連携ハンドブックで紹介した方法を転用しました。

まとめ
非IT部門のExcel地獄から脱却するには、段階的なアプローチと現場を巻き込む推進力が欠かせません。現状を可視化し、クイックウィンで成果を示し、本格的な再設計に繋げる。この流れをPjMがリードすることで、Excel依存から解放され、業務全体の生産性が向上します。
今日からできるアクションとして、次の3つを提案します。指標設計の具体例はMeasure What Matters(OKR)で紹介されているKPIレビュー手法が参考になります。
– 現状を測る: 月次業務の工数とミス発生率を可視化し、改善対象を明確にする。
– 小さな改善を試す: ピボットテーブルやPower Queryなど、即効性のある手段から着手する。
– 定着の仕組みを整える: キーパーソンを巻き込み、継続的に改善提案を募る体制を作る。
Excel改善のゴールは、単にツールを変えることではありません。現場の人たちが「もっと価値ある仕事に時間をかけられる」状態を実現することです。今日から一歩踏み出し、あなたの組織のDX推進に弾みをつけましょう。