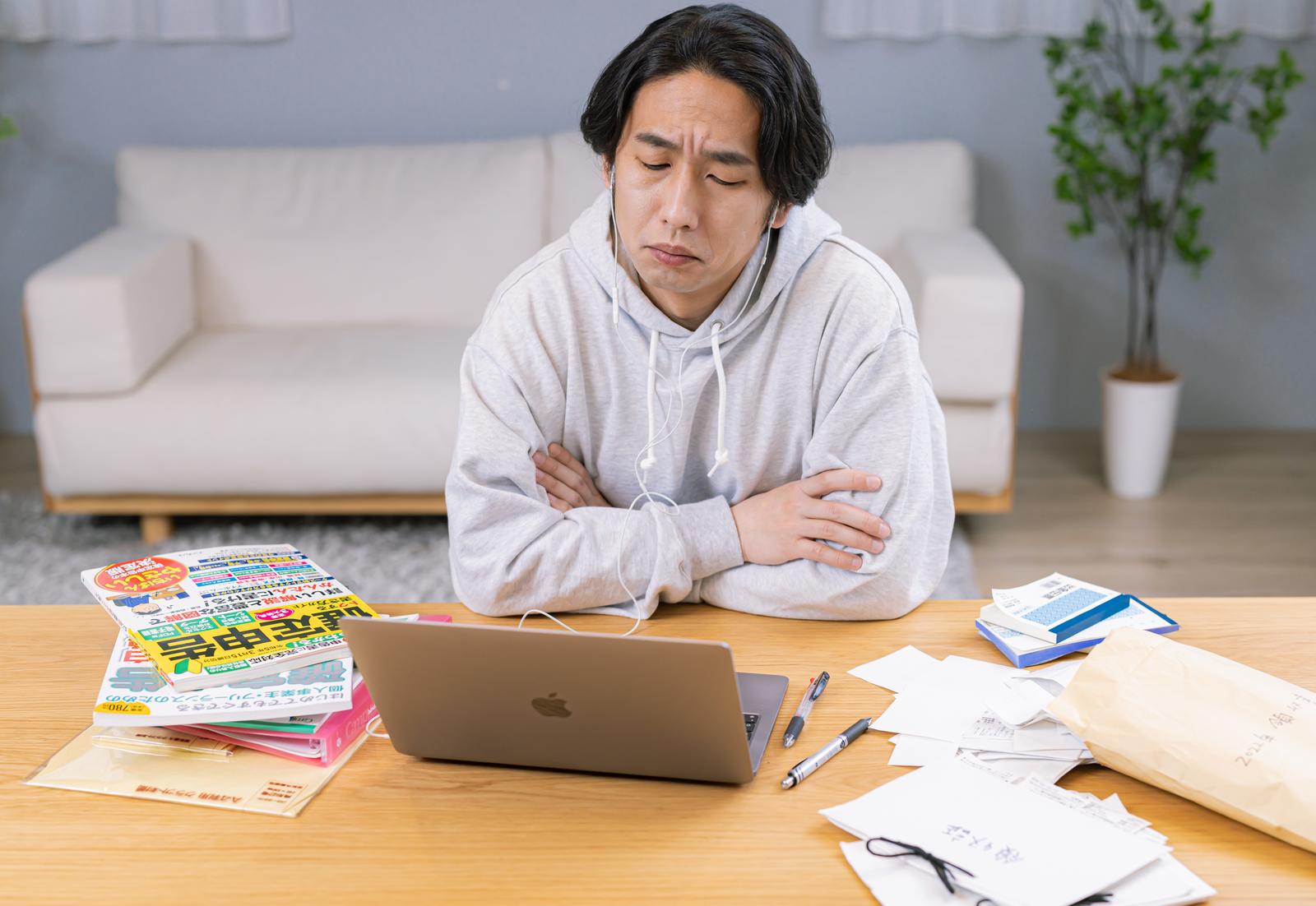こんばんは!IT業界で働くアライグマです!
「エンジニアがいない会社で起業したいんですが、どう思いますか?」—。知人の経営者からこんな相談を受けたとき、私は正直に答えました。「それは、コックがいないレストランを開くようなものです」と。
現代のビジネスにおいて、ITシステムは単なる「道具」ではありません。顧客との接点、業務の効率化、データ分析による意思決定、そして競合他社との差別化。これらすべてが、技術によって支えられています。にもかかわらず、多くの起業家が「エンジニアは後から雇えばいい」「外注すれば何とかなる」と考え、技術を軽視したまま事業をスタートさせてしまいます。
PjMとして、そして一人のエンジニアとして、私は数多くの企業のプロジェクトに関わってきました。その中で目撃してきたのは、技術を軽視した企業の悲惨な末路と、逆に技術を重視した企業の劇的な成長です。
この記事では、なぜエンジニアがいない起業が99%失敗するのか、その根本的な理由を解き明かし、成功する技術系起業の条件について、実際のプロジェクト事例をもとに解説していきます。
エンジニアがいない起業が失敗する3つの致命的理由
技術的負債の雪だるま式増大
最も深刻な問題は、技術的負債の蓄積です。エンジニアがいない状況で外注やノーコードツールに頼った開発を行うと、短期的にはサービスが動いているように見えても、内部では深刻な問題が潜んでいます。
私が関わったあるECサイトの事例では、創業時に「とりあえず動けばいい」という方針で外注開発されたシステムが、わずか1年後には完全に破綻していました。商品数が増えるたびにページの表示速度が遅くなり、注文処理でエラーが頻発。最終的には、システム全体を一から作り直すことになり、開発費用は当初の3倍に膨れ上がりました。
技術的負債とは、将来の保守性や拡張性を犠牲にして、短期的な開発速度を優先した結果生まれる「借金」のようなものです。この借金は、複利のように指数関数的に増大し、やがて事業の成長を完全に阻害します。
エンジニアがいない企業では、この負債の存在すら認識できないのが最大の問題です。経営者は「システムが動いているから大丈夫」と考えますが、水面下では確実に企業の競争力が蝕まれているのです。
迅速な意思決定と実装のボトルネック
現代のビジネス環境では、スピードが生命線です。市場の変化に応じて機能を追加したり、競合の動きに対応したりするためには、技術的な変更を迅速に実行できる体制が不可欠です。
しかし、エンジニアがいない企業では、すべての技術的変更が外部ベンダーとの調整を必要とします。「この機能を追加したい」と思っても、まず外注先に相談し、見積もりを取り、契約を結び、開発を待つ。この一連のプロセスには、最低でも数週間から数ヶ月かかります。
私が支援したある企業では、競合他社が新機能をリリースしたのを受けて、類似機能の追加を検討していました。しかし、社内にエンジニアがいないため、外注先との調整だけで1ヶ月が経過。実際の開発に3ヶ月、テストと修正に1ヶ月かかり、競合から半年遅れでのリリースとなりました。その頃には、市場の関心は既に次のトレンドに移っており、機能追加の効果はほとんど得られませんでした。
一方、社内にエンジニアがいる企業では、朝のミーティングで決まった方針が、その日の夕方には実装されているということも珍しくありません。この差は、競争の激しい現代において、決定的な優劣を生みます。
技術的視点を欠いた戦略立案
最も見落とされがちですが、実は最も重要なのが戦略立案における技術的視点の欠如です。エンジニアがいない経営陣は、技術的な制約や可能性を理解せずに事業計画を立ててしまいます。
「AIを使った革新的なサービス」「ブロックチェーンを活用した新しいビジネスモデル」といった魅力的に聞こえるアイデアも、技術的な実現可能性や開発コスト、運用の複雑さを考慮せずに立案されると、単なる絵に描いた餅になってしまいます。
逆に、技術的な視点があれば、「既存の技術を組み合わせることで、低コストで大きな価値を生み出せる」アイデアを発見することもできます。技術を知らない経営者は、往々にして過度に複雑なソリューションを求めたり、逆に技術的な優位性を軽視したりする傾向があります。
実際の起業において、技術がビジネスの根幹を支える以上、技術を理解しない経営は、設計図なしに建物を建てるようなものです。一時的には形になったように見えても、必ず破綻の時がやってきます。
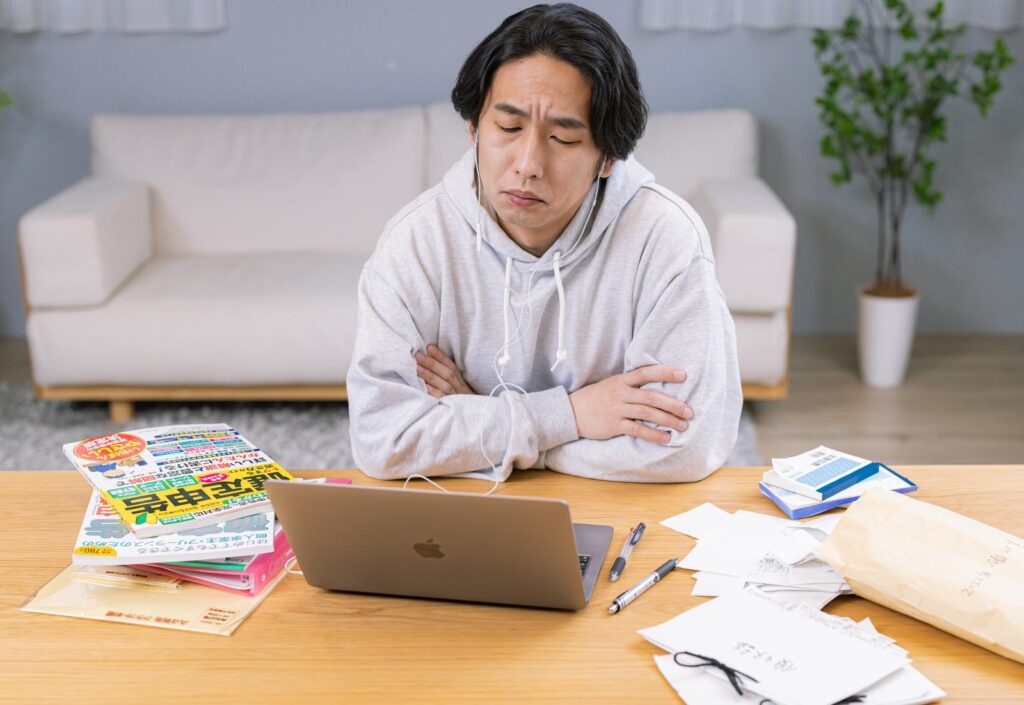
成功する技術系起業の3つの条件
では、どうすれば技術を活かした成功する起業ができるのでしょうか。私がこれまで関わったプロジェクトの中で、特に印象的な成功事例から導き出した、3つの条件をご紹介します。
創業メンバーに必ずエンジニアを含める
最も確実な方法は、創業メンバーの中に技術的なバックグラウンドを持つ人物を含めることです。これは単にCTOを雇うということではありません。経営陣の一人が、技術的な判断を下せる人物であることが重要です。
成功事例として挙げたいのが、私が初期から関わっているあるSaaSスタートアップです。創業者はビジネス畑出身でしたが、共同創業者として経験豊富なフルスタックエンジニアを迎えました。この技術的パートナーの存在により、以下のような効果が生まれました。
迅速なプロトタイプ開発: アイデアから最初のプロトタイプまで、わずか2週間で完成。市場での反応を早期に確認できました。
技術的負債の予防: 初期段階から将来の拡張を見据えた設計により、ユーザー数が100倍になっても安定稼働を維持。
競合優位性の確立: 技術的な差別化要素を活かし、後発ながら市場シェア上位に食い込みました。
創業チームに技術者がいることで、事業計画の段階から技術的実現可能性が考慮され、無謀な計画や過度に保守的な計画を避けることができます。また、資金調達の際も、投資家からの技術的な質問に自信を持って答えることができ、より有利な条件での調達が可能になります。
技術投資を「コスト」ではなく「資産」として捉える
多くの経営者が犯す過ちは、技術開発を単なるコストセンターとして扱うことです。しかし、成功する起業家は、技術を「将来の収益を生み出す資産」として投資します。
ここで重要なのは、技術投資の効果を正しく測定し、評価することです。単純な開発費用だけでなく、技術によってもたらされる以下のような価値を定量化する必要があります。
業務効率化による人件費削減: 自動化により、手作業で必要だった人員を他の付加価値業務に配置転換
顧客満足度向上による売上増: システムの高速化や機能改善により、顧客継続率が向上
データ活用による意思決定精度向上: 適切なデータ収集・分析基盤により、マーケティングROIが改善
私が支援したあるEC企業では、レコメンドエンジンの開発に200万円を投資しました。一見すると大きなコストに見えますが、導入後3ヶ月で平均注文額が15%向上し、年間売上の増加額は投資額の10倍以上になりました。
技術を資産として捉える経営者は、継続的な技術投資を行い、それが複利効果を生んで長期的な競争優位を築きます。
現代の起業において、技術的基盤の重要性はますます高まっています。これからの時代に起業を成功させるための考え方や戦略について、より深く学びたい方には、以下の書籍が強くお勧めです。
サイエンス・オブ・アントレプレナーシップ感覚や経験に頼らず、科学的なアプローチで起業の成功確率を最大化する方法論が、この一冊に凝縮されています。
段階的な技術体制構築
最後の条件は、事業の成長段階に応じた技術体制の段階的構築です。創業初期から大規模な技術チームを抱える必要はありませんが、事業の成長と歩調を合わせて技術力を強化していく計画的なアプローチが重要です。
成功する起業の技術体制構築は、一般的に以下のようなステップを踏みます:
フェーズ1(創業期): 創業メンバーまたは少数精鋭のエンジニアによるMVP(最小限の実行可能な製品)開発
フェーズ2(成長期): 専任エンジニアの採用と、基本的な開発プロセス・ツールの整備
フェーズ3(拡大期): チーム化と役割分担、品質管理体制の確立
フェーズ4(成熟期): 技術的負債の整理と次世代技術への投資
重要なのは、各フェーズで「今必要な技術力」と「次のフェーズで必要になる技術力」の両方を見据えることです。前者が不足すれば現在の事業が回らなくなり、後者の準備を怠れば成長の機会を逃してしまいます。
私がアドバイザーとして関わったあるFinTechスタートアップでは、この段階的構築を徹底することで、創業から3年で従業員数50名のうち15名がエンジニアという理想的な技術組織を構築できました。各フェーズで適切なタイミングで技術投資を行ったことで、市場の変化に迅速に対応できる技術的アジリティを維持しています。

私が目撃した「技術軽視」の悲惨な末路
ここで、実際に私が関わったプロジェクトの中から、技術を軽視したことで失敗に終わった企業の事例をご紹介します。これは決して他人事ではなく、多くの起業家が陥りがちな罠でもあります。
事例1:外注依存で自滅した旅行予約サイト
3年前、ある旅行関連のスタートアップから「システムが不安定で困っている」という相談を受けました。話を聞くと、創業時に300万円で外注開発したWebサービスが、ユーザー数の増加とともに様々な問題を抱えるようになったとのことでした。
調査してみると、問題は深刻でした:
データベース設計の破綻: ユーザー数が1万人を超えた頃から、検索処理に30秒以上かかるように。根本的な設計見直しが必要でした。
セキュリティの脆弱性: 個人情報保護の基本すらできておらず、一歩間違えば大規模な情報漏洩事故につながる状態でした。
拡張性の欠如: 新機能追加のたびに既存機能が不安定になり、修正に膨大な工数がかかっていました。
最終的に、この企業はシステム全体の作り直しに1,500万円を投じることになりました。しかし、その間に競合他社に顧客を奪われ、市場での立ち位置を大きく失うことになったのです。
もし創業時から技術的な視点があれば、初期投資を少し増やすだけで、このような事態は回避できたはずです。技術を軽視したことで、結果的に当初の5倍のコストと、取り返しのつかない機会損失を被ることになったのです。
事例2:AIブームに乗り遅れたマーケティング会社
もう一つは、従来のマーケティング手法で成功していた企業が、AI技術の波に完全に乗り遅れた事例です。
この企業の経営陣は「AIなんて流行りもの」「我々の経験とノウハウがあれば十分」と考え、技術投資を軽視していました。しかし、競合他社が機械学習を使った広告最適化や、自然言語処理による顧客分析を導入する中で、徐々に競争力を失っていきました。
顧客満足度の低下: 従来手法では限界があり、ROIの改善が頭打ちに
人材の流出: 技術的なチャレンジを求める優秀な社員が、より先進的な企業に転職
新規顧客獲得の困難: 提案内容が時代遅れとなり、大型案件を逃すように
結局、この企業は2年前から慌てて技術者の採用とAI導入を進めていますが、先行企業との差は開く一方です。技術の重要性に気づいたときには、すでに手遅れだったのです。
これらの事例が示すのは、技術軽視の代償は単なる開発コストの増加に留まらないということです。市場での競争力、顧客の信頼、そして事業の継続可能性そのものが危険にさらされるのです。

起業前に準備すべき技術的基盤
では、これから起業を考えている方は、どのような技術的準備をすべきでしょうか。PjMとして数多くのプロジェクトを見てきた経験から、最低限準備しておくべき3つの要素をお伝えします。
基本的なITリテラシーの習得
まず経営者自身が、基本的なITリテラシーを身につけることが重要です。プログラミングができる必要はありませんが、技術者との会話ができ、技術的な判断の妥当性を評価できるレベルの知識は必須です。
具体的には以下のような知識が求められます:
システム構成の基本理解: フロントエンド、バックエンド、データベースの役割と関係性
開発プロセスの理解: アジャイル開発、DevOps、CI/CDなどの現代的な開発手法
セキュリティの基礎知識: 一般的な脅威と対策、コンプライアンス要件
クラウドサービスの活用: AWS、Azure、GCPなどの主要サービスの概要
これらの知識があることで、技術者との意思疎通がスムーズになり、適切な技術的意思決定を下せるようになります。
信頼できる技術パートナーの確保
社内に技術者を抱えられない場合でも、信頼できる技術パートナーを事前に確保しておくことが重要です。ただし、単なる外注先ではなく、事業の成功を共に目指すパートナーシップを築ける相手を選ぶ必要があります。
良い技術パートナーの条件:
事業理解力: 技術的な実装だけでなく、ビジネス的な価値を理解している
長期的視点: 目先の利益より、持続可能な技術基盤構築を重視している
透明性: 技術的な課題やリスクを隠さず、率直にコミュニケーションを取れる
成長性: 事業の拡大に合わせて、サポート体制を強化できる
理想的なのは、将来的に社内エンジニアとして引き抜けるような人材との関係性を築くことです。
技術パートナーシップの重要性や、効果的なチーム構築について理解を深めたい方には、現代のビジネスチーム論について書かれたこちらの書籍が参考になります。
技術者とビジネス側という異なるバックグラウンドを持つメンバーが、いかにして共通のビジョンを共有し、困難を乗り越えるチームを作るか。その具体的な方法論が、この一冊に詰まっています。
段階的な技術投資計画の策定
最後に、事業計画と連動した技術投資計画を策定することが重要です。「いつ、どのような技術的強化が必要になるか」を事前に想定し、それに必要な予算と人材を計画に織り込みます。
技術投資計画に含めるべき要素:
インフラ投資: サーバー、クラウドサービス、セキュリティ対策
人材投資: エンジニア採用、教育研修、外注費用
ツール投資: 開発ツール、プロジェクト管理ツール、監視システム
R&D投資: 新技術調査、プロトタイプ開発、技術的実験
これらの投資を「コスト」ではなく「将来の収益を生み出すための先行投資」として位置付け、適切なタイミングで実行することが、持続的な成長を実現する鍵となります。
特に重要なのは、競合他社の動向や技術トレンドを常に監視し、投資計画を柔軟に調整することです。技術の進歩は非線形であり、突然の技術革新が事業環境を一変させることもあります。そうした変化に迅速に対応できる技術的基盤と投資余力を確保しておくことが、現代の起業には不可欠なのです。

まとめ
現代のビジネス環境において、「エンジニアがいない起業」は、武器を持たずに戦場に向かうようなものです。一時的に運良く生き残れたとしても、長期的な成功は極めて困難と言わざるを得ません。
本記事で解説した通り、技術軽視の代償は想像以上に深刻です。技術的負債の蓄積、意思決定スピードの低下、戦略立案における視点の欠如。これらの問題は、事業が成長するにつれて指数関数的に深刻化し、最終的には企業の存続すら脅かします。
一方で、技術を正しく理解し、適切に活用できる起業家には、無限の可能性が開かれています。創業メンバーへのエンジニア参画、技術投資の資産化、段階的な技術体制構築。これらの条件を満たすことで、競合他社を大きく引き離す競争優位を築くことができるのです。
重要なのは、技術を「後から何とかなるもの」ではなく、「事業の根幹を支える重要な基盤」として認識することです。その認識があってこそ、適切なタイミングで適切な技術投資を行い、持続的な成長を実現できるのです。
これから起業を考えている方、あるいは技術軽視で悩んでいる経営者の方にとって、この記事が技術の重要性を再認識し、より良い意思決定を行うためのきっかけとなれば幸いです。技術と経営の両方を理解した起業家こそが、これからの時代を勝ち抜いていけるのです。