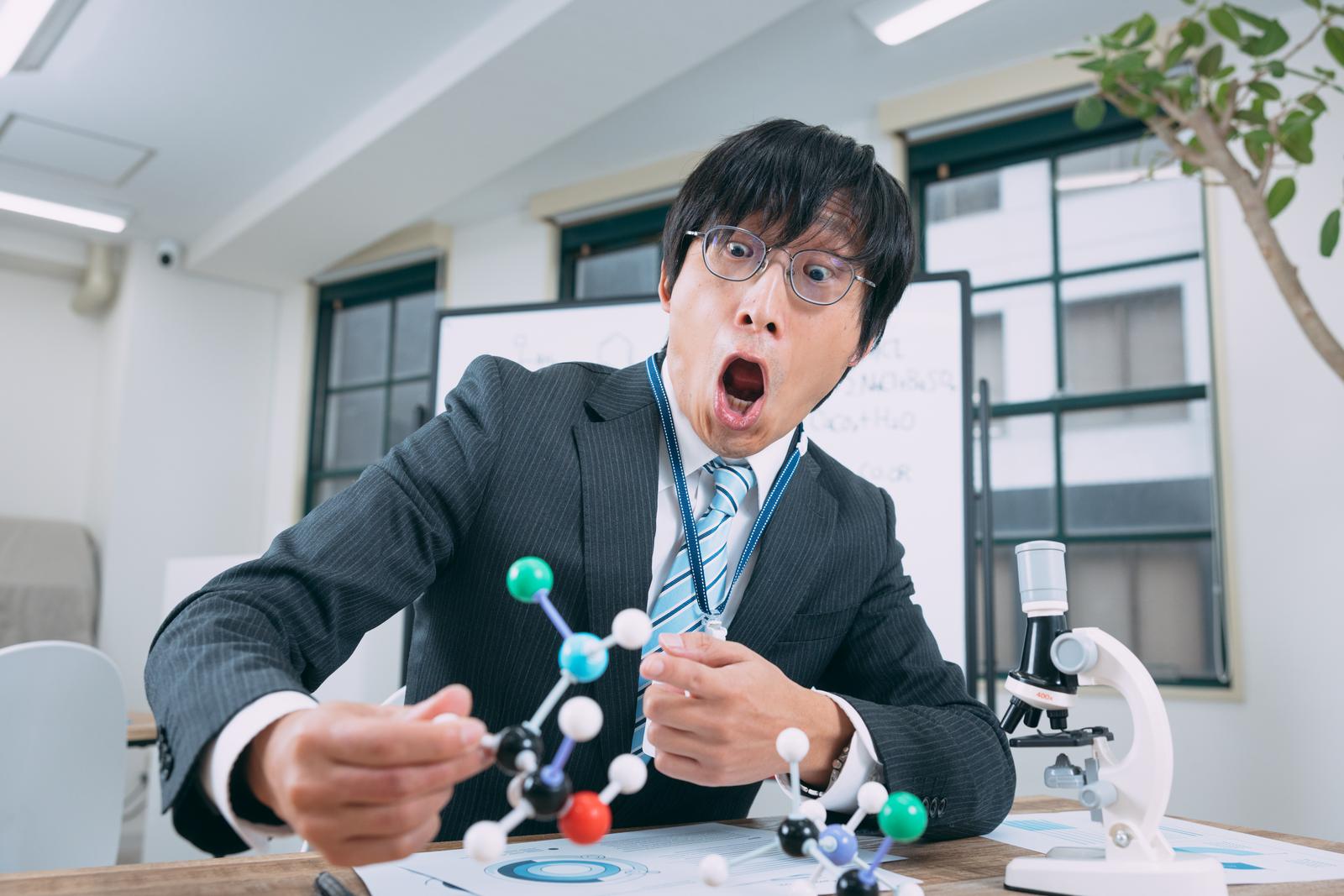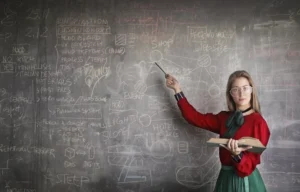こんばんは!IT業界で働くアライグマです!
「うちのチームのチケット管理?ああ、共有サーバーにある秘伝のExcelファイルでやってるよ」
多くの開発現場、特に歴史の長いプロジェクトや、非IT部門との連携が多いチームで、いまだにこのような光景が見られます。私のブログの検索データを見ても、「チケット管理 excel」というキーワードでの検索は一向になくなる気配がありません。
手軽に始められ、誰もが一度は使ったことがあるExcelは、一見すると非常に便利なツールに思えます。しかし、プロジェクトが少しでも複雑になり、関わる人が増え、時間が経過すると、その「手軽さ」はあっという間に牙を剥きます。
- 「あれ、俺が昨日更新したはずなのに、内容が元に戻ってる…?」
- 「最新版ってファイル名にFinalってついてるやつ?いや、Final_2の方か…?」
- 「半年前のあの障害の対応、どうやったっけ…?Excelファイルが重すぎて検索もままならない…」
このような非効率という名の“時間泥棒”が、あなたのチームの開発スピードを静かに、しかし確実に蝕んでいるとしたら…?
この記事では、もはや現代開発における「技術的負債」とさえ言えるExcelによるチケット管理の限界を解き明かし、JiraやRedmineといったモダンな専用ツールへスムーズに移行するための具体的なステップ、そしてその先にあるAIを活用した次世代のチケット管理術まで、あなたのチームの生産性を劇的に向上させるためのノウハウを、私のPjMとしての経験を交えながら徹底的に解説します。
なぜExcelでのチケット管理は“必ず”破綻するのか?
「うちはうまくやれてる」と思っているチームも、それはまだプロジェクトの規模が小さいか、あるいは誰か一人のスーパーマン的なメンバーの献身的な努力によって、かろうじて成り立っているに過ぎません。Excel管理は、構造的に以下の問題を抱えており、プロジェクトの成長と共に必ず破綻します。
破綻の理由1:リアルタイム性の完全な欠如と情報の分断
Excelの共有ファイルは、基本的に誰か一人が開いていると他の人は編集できません(共同編集機能もありますが、競合やデータ破損のリスクは常につきまといます)。これにより、「Aさんが更新中だから、後でやろう」と思ったタスクが忘れ去られたり、Bさんがローカルにコピーした古いファイルに追記してしまい、情報の先祖返りが発生したりします。
結局、情報の信頼性が担保できないため、毎朝の朝会で「あの件、どうなってる?」と口頭で確認する羽目になり、多大なコミュニケーションコストが発生します。この問題については、「なぜIT業界の会議は長引くのか?」でも触れています。
破綻の理由2:属人化という名のブラックボックス
多くの場合、Excel管理ファイルは、最初に作った人の「俺流」ルールで満ち溢れています。特定のセルの色は何を意味するのか、このプルダウンリストにないステータスはどうすればいいのか…。作成者本人しかわからないルールが蔓延し、その人が異動や退職した途端、誰も触れないブラックボックスと化します。これでは、チームとしての継続的な改善は望めません。
破綻の理由3:検索性と分析機能の致命的な欠如
「過去の類似チケットを探して参考にしたい」と思っても、Excelの検索機能では限界があります。全文検索は遅く、複数の条件を組み合わせた柔軟なフィルタリングも困難です。
また、プロジェクトの状況を分析しようにも、「今月、何件のバグをクローズできたか」「どの機能の実装に最も時間がかかっているか」といったデータを集計するためには、手作業で関数を駆使する必要があり、レポート作成だけで一日が終わってしまいます。これでは、データに基づいたボトルネックの特定や改善活動など夢のまた夢です。
破綻の理由4:外部ツールとの連携性の皆無
現代の開発は、Git(GitHub, GitLab)、Slack(Teams)、CI/CDツールなど、様々なツールとの連携が前提です。モダンなチケット管理ツールなら、「このチケットは、このコミットで修正された」「このチケットが更新されたら、Slackの特定チャンネルに通知する」といった連携が容易に実現できます。
しかし、Excelは孤島です。すべての連携は、エンジニアのコピペという手作業に依存し、情報のサイロ化(孤立)を加速させます。
これらの問題は、チームの規模が大きくなるほど、プロジェクトが長くなるほど深刻化し、最終的には管理コストが開発コストを上回るという、本末転倒な事態に陥るのです。
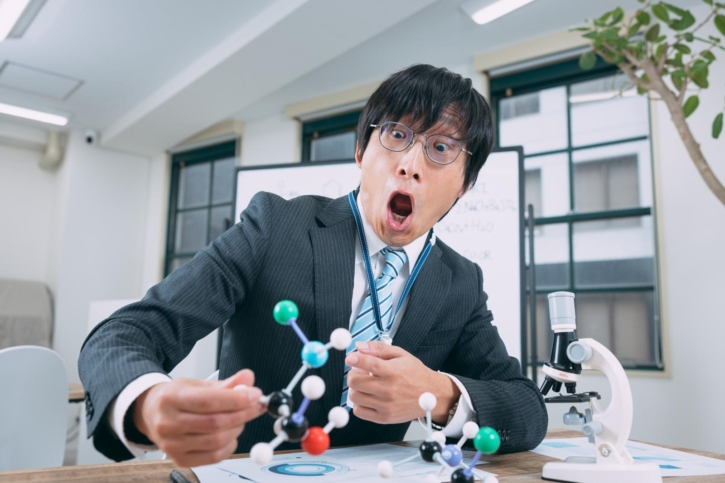
モダンなチケット管理ツールへの移行という“次の一手”
Excelの限界を克服するために、今すぐ専用のチケット管理ツール(BTS: Bug Tracking System / ITS: Issue Tracking System)の導入を検討しましょう。ここでは、数あるツールの中から、特に代表的で実績のあるものを紹介します。
代表的なチケット管理ツールとその特徴
| ツール名 | 特徴 | 向いているチーム |
|---|---|---|
| Jira | アジャイル開発のデファクトスタンダード。カスタマイズ性が非常に高く、大規模開発に対応可能。 | アジャイル開発を本格的に実践したい中〜大規模チーム。 |
| Redmine | オープンソースで無料。プラグインが豊富で、ガントチャートなど伝統的な管理手法にも強い。 | コストを抑えたいチーム。自社で柔軟にカスタマイズしたいチーム。 |
| Backlog | 日本のヌーラボ社が開発。UIが直感的で、非エンジニアにも分かりやすい。ガントチャートやGit連携も強力。 | エンジニア以外のメンバーも多く関わる、日本のビジネス環境にフィットさせたいチーム。 |
| GitHub Issues | GitHubに統合されており、開発ワークフローとの連携が最もスムーズ。マークダウンで記述できる。 | 開発者が中心の小〜中規模チーム。オープンソースプロジェクト。 |
| Asana / Trello | カンバンボードが中心で、UIが非常に直感的。タスク管理ツールとしての側面が強い。 | 小規模チームや、個人のタスク管理から始めたい場合。 |
失敗しないツールの選定ポイント
「よし、Jiraを導入しよう!」とトップダウンで決めても、現場にフィットしなければ形骸化してしまいます。ツール選定で失敗しないために、以下の観点でチームメンバーと議論することが重要です。
- チームの文化と開発手法: まずは自分たちのチームの現状を直視しましょう。厳密なアジャイルをやりたいのか、それともまずはカンバンでタスクを見える化するところから始めたいのか。
- コスト感覚: クラウド版の月額費用(ユーザー数課金)は許容できるか。それとも、初期構築と運用の手間をかけてでもオープンソースを選ぶか。
- 連携の重要度: GitHub/GitLabとの連携は必須か。Slack/Teamsへの通知はどのレベルで必要か。
- 誰が使うのか: エンジニアだけで使うのか、それとも企画や営業、サポートチームも巻き込むのか。ユーザー層によって、求められるUIのシンプルさは大きく変わります。
ツール導入は、単なるツールの入れ替えではなく、チームの働き方を変えるプロジェクトです。まずは小規模なチームで無料プランやトライアルを試し、自分たちのチームに最もフィットするツールを、ボトムアップで見つけていくアプローチが成功の鍵となります。このプロセス自体が、チームビルディングの素晴らしい機会にもなります。
チームで新しい挑戦を始める際には、こちらの書籍が非常に参考になります。ツールという「手段」の前に、チームという「目的」を考えるきっかけを与えてくれるはずです。
チーム・ジャーニー

脱Excel!移行プロジェクトを成功させる5ステップ
ツールの選定が終わっても、油断は禁物です。Excelからの移行は、多くの抵抗と困難を伴うミニプロジェクトです。これを成功させるための具体的なステップを解説します。
ステップ1:目的の共有とチャンピオンの任命
まず、「なぜExcelをやめて、新しいツールを導入するのか」という目的を、チーム全員で共有します。生産性の向上、属人化の排除、ナレッジの蓄積など、具体的なメリットを提示し、全員の納得感を得ることが重要です。そして、この移行プロジェクトを推進する「チャンピオン(推進役)」を任命しましょう。
ステップ2:シンプルな運用ルールの策定
高機能なツールを導入したからといって、最初から全ての機能を使おうとしてはいけません。まずは、Excelで管理していた項目をベースに、チケットのステータス(例:ToDo, InProgress, Done)や、優先度(High, Middle, Low)といった、最小限のルールだけを決めます。ルールは、運用しながらチームで育てていくものです。
ステップ3:過去データの移行(割り切りが重要)
Excelに溜まった過去のチケットをどうするかは、大きな問題です。全てを移行しようとすると、膨大なコストがかかります。ここでのポイントは割り切りです。
- 進行中のチケットのみ移行する
- 過去1年分のデータのみ、CSVインポート機能で移行する
- それ以前のデータは、Excelファイルのまま「過去の遺産」として参照専用で保管する
といった判断が、プロジェクトをスムーズに進める上で賢明です。
ステップ4:並行運用とトレーニング期間
いきなりExcelを廃止するのではなく、最初の1〜2週間は、Excelと新しいツールを並行で運用する期間を設けます。これは、新しいツールに慣れるためのトレーニング期間です。この間に、ツールの使い方に関する勉強会を開いたり、質問しやすい雰囲気を作ったりすることが重要です。
ステップ5:完全移行と改善サイクルの開始
チームが新しいツールに慣れてきたら、Excelファイルを読み取り専用にし、完全に新しいツールに移行します。そして、移行して終わりではありません。週に一度の振り返り(レトロスペクティブ)などで、「この運用ルールは分かりにくい」「もっとこうすれば便利になる」といった意見を出し合い、継続的にワークフローを改善していくサイクルを回し始めることが、本当のゴールです。

その先へ:AIでチケット管理を“超”効率化する未来
モダンなツールを導入するだけでも生産性は劇的に向上しますが、AIの進化は、チケット管理をさらに次のステージへと引き上げようとしています。
チケット起票とトリアージの完全自動化
SentryやDataDogといったエラー監視ツールと連携し、検知したエラーログをAIが解析。自動でチケットを起票し、内容の重要度や影響範囲を判断して優先度を決定。さらに、コードの変更履歴(git blame)から、そのエラーを埋め込んだ可能性が最も高い担当者を自動でアサインする。そんな未来がすぐそこまで来ています。
自然言語でのチケット作成と要件定義
Slack上で「ユーザーがログインできないらしい。調査お願い」と投稿するだけで、AIがその内容を解釈し、必要な項目(再現手順、期待する結果など)をヒアリング形式で補完しながら、正式なチケットを自動で作成してくれます。これにより、非エンジニアでも質の高いチケットを簡単に起票できるようになります。
過去のナレッジの自動サジェスト
新規チケットが作成された際、AIが過去の膨大なチケットデータベースや社内ドキュメントを瞬時に検索し、「このチケットは、3ヶ月前に解決した〇〇と類似しています。担当者はAさんで、こちらのドキュメントを参考に修正されました」と、関連チケットやナレッジを自動で提示します。これにより、同じ問題で何度も時間を浪費する、という悲劇を防ぎます。
これらの機能の一部は、すでにJiraのAIアドオンなどで実現され始めており、今後はZapier/MakeといったiPaaSツールとOpenAI APIなどを組み合わせることで、よりカスタマイズされたAIワークフローを構築することも可能になるでしょう。
質の高いチケットを書くためには、「バグ」と「エラー」の違いを明確に意識することが重要です。この点については、以前こちらの記事「バグとエラーの違いって何?IT用語の基礎知識」で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

まとめ
チケット管理は、プロジェクトの健全性を示すバロメーターであり、開発プロセスを円滑に進めるための土台です。
Excelによる場当たり的で非効率な管理から脱却し、チームの文化や規模に合った専用ツールを導入することは、もはや現代の開発現場における“衛生要因”、つまり、あって当たり前の必須事項と言えるでしょう。
そして、その先にはAIによる自動化・効率化という、エンジニアがより創造的で価値ある仕事に集中できる未来が待っています。
煩雑な管理業務から解放され、エンジニアが本来の実力を最大限に発揮できる環境を整えること。それこそが、プロジェクトマネージャーやリーダーに課せられた最も重要な責務の一つです。
まずは第一歩として、あなたのチームの「秘伝のExcelファイル」を開き、そこにどれだけの無駄と非効率が眠っているかを、チームメンバーと話し合ってみてはいかがでしょうか。