こんばんは!IT業界で働くアライグマです!
「パスワードを平文(ひらぶん、プレーンテキスト)でデータベースに保存している」——この事実を聞いて、あなたはどのように感じるでしょうか? もし「特に問題ないのでは?」と感じたなら、そのシステムはセキュリティ的に「平成」の時代に取り残されていると言わざるを得ません。現代のWebサービスやシステムにおいて、パスワードをそのままの文字列で保存することは、極めて危険な行為であり、絶対に避けるべきです。
この記事では、なぜパスワードを平文で保存することが「時代遅れ」で「危険」なのか、そして令和の時代にふさわしい、安全なパスワード管理方法とはどのようなものなのかを、開発者、システム管理者、そしてセキュリティに関心のあるすべての方に向けて詳しく解説していきます。自社のシステム、あるいは利用しているサービスは大丈夫か、ぜひこの記事を読んで確認してみてください。
パスワードを平文で保存するとは?
まず、「平文で保存する」とはどういうことか具体的に説明します。これは、ユーザーがアカウント登録時やパスワード変更時に入力したパスワード文字列(例: “password123″)を、そのままの形でデータベースに記録しておくことを指します。暗号化やハッシュ化といった、読み取れないようにするための処理が一切施されていない状態です。
一見すると、管理が簡単なように思えるかもしれません。しかし、この単純さが、後に取り返しのつかない事態を引き起こす可能性があるのです。

なぜ平文パスワードは「平成」レベルの危険なのか?
パスワードを平文で保存することが、なぜこれほどまでに問題視されるのでしょうか。その理由は多岐にわたりますが、主に以下の点が挙げられます。
情報漏洩時の甚大な被害
最大の理由は、データベースが何らかの理由で侵害された場合の影響が壊滅的になることです。サイバー攻撃、内部不正、設定ミスなどにより、悪意のある第三者がデータベースにアクセスした場合、そこに平文で保存されているパスワードは完全に読み取り可能な状態で流出してしまいます。
流出したパスワードは、そのサービスへの不正ログインに直結します。個人情報の閲覧・改ざん、登録されたクレジットカード情報の悪用、なりすましによる詐欺行為など、ユーザーに計り知れない被害をもたらす可能性があります。企業の信用失墜はもちろん、損害賠償請求に発展するリスクも極めて高いと言えるでしょう。
パスワードリスト攻撃のリスク増大
多くのユーザーは、残念ながら複数のサービスで同じ、あるいは類似したパスワードを使い回す傾向があります。あるサービスから平文のパスワードリストが漏洩すると、攻撃者はそのリストを使って他の人気サービス(SNS、ネットバンキング、ECサイトなど)への不正ログインを試みます。これが「パスワードリスト攻撃」です。
あなたのサービスで平文パスワードを保存しているということは、間接的に他のサービスのセキュリティをも脅かすことに繋がりかねません。漏洩元として特定されれば、社会的な非難を浴びることは避けられないでしょう。
法令遵守と信頼性の問題
個人情報保護法などの法令では、事業者は個人データを安全に管理するための措置を講じる義務があります。パスワードは認証における重要な情報であり、それを平文で保存することは、安全管理措置義務違反とみなされる可能性が高いです。万が一漏洩事故が発生した場合、行政からの指導や罰則を受けるリスクがあります。
また、セキュリティ対策が不十分であるという事実は、顧客や取引先からの信頼を著しく損ないます。一度失った信頼を取り戻すことは容易ではありません。サービス利用者の離脱、新規顧客獲得の困難化、ブランドイメージの低下など、事業継続に深刻な影響を与えるでしょう。
技術的な時代遅れ感
パスワードを安全に保存するための技術(ハッシュ化、ソルトなど)は、何年も前から確立されており、実装も比較的容易になっています。現代において、パスワードを平文で保存しているシステムは、技術的に著しく時代遅れであり、開発者や管理者のセキュリティ意識の低さを露呈していると言わざるを得ません。
「平成」という言葉で表現したのは、まさにこの時代遅れ感を強調するためです。令和の時代には、もはや許容されるべきではないプラクティスなのです。

あるべきパスワード管理:ハッシュ化とソルト
では、どのようにパスワードを管理するのが現代のスタンダードなのでしょうか。鍵となるのは「ハッシュ化」と「ソルト」です。
ハッシュ化とは?
ハッシュ化とは、元のデータを特定の計算手順(ハッシュ関数)によって、別の固定長の不規則な文字列(ハッシュ値)に変換する処理のことです。重要な特徴は以下の通りです。
- 一方向性(不可逆性): ハッシュ値から元のデータを復元することは、計算上ほぼ不可能です。
- 入力感度: 元のデータが少しでも異なれば、生成されるハッシュ値は全く異なるものになります。
- 衝突耐性: 異なるデータから同じハッシュ値が生成される(衝突)可能性が極めて低い。
パスワードをデータベースに保存する際は、パスワードそのものではなく、パスワードをハッシュ化した後のハッシュ値を保存します。ユーザーがログインする際には、入力されたパスワードを同じハッシュ関数でハッシュ化し、データベースに保存されているハッシュ値と一致するかどうかを比較して認証を行います。これにより、データベースが漏洩しても、元のパスワードが直接知られることはありません。
代表的なハッシュ関数としては、SHA-256、SHA-3、bcrypt、Argon2などがあります。現在推奨されるのは、bcryptやArgon2のように、意図的に計算コストを高める機能を持つアルゴリズムです。
ソルトの重要性
ハッシュ化だけでは、「レインボーテーブル攻撃」と呼ばれる手法に弱い場合があります。レインボーテーブルとは、よく使われるパスワードとそのハッシュ値の対応表をあらかじめ計算しておき、漏洩したハッシュ値と照合することで元のパスワードを推測する攻撃です。
この対策として用いられるのが「ソルト」です。ソルトとは、ユーザーごとに生成されるランダムな文字列のことです。パスワードをハッシュ化する際に、このソルトをパスワードに付加してからハッシュ計算を行います。
ハッシュ値 = ハッシュ関数(パスワード + ソルト)
そして、データベースにはハッシュ値と共に、使用したソルトも保存しておきます(ソルト自体は秘密情報ではありません)。
ソルトを使うことで、たとえ同じパスワードを使っているユーザーが複数いたとしても、ソルトが異なるため、データベースに保存されるハッシュ値はユーザーごとに異なるものになります。これにより、レインボーテーブルを用いた攻撃は極めて困難になります。ソルトは、現代のパスワード保護において必須の要素です。
ストレッチング(キー派生関数)
さらにセキュリティ強度を高めるために、「ストレッチング」または「キー派生関数」と呼ばれる技術が用いられます。これは、ハッシュ計算を意図的に複数回繰り返したり、計算に必要なメモリ量を増やしたりすることで、1回のハッシュ計算にかかる時間を長くする手法です。
通常のログイン処理では、計算時間の増加はユーザー体験にほとんど影響を与えません。しかし、攻撃者がパスワードを推測するために行う総当たり攻撃(ブルートフォース攻撃)や辞書攻撃では、膨大な回数のハッシュ計算が必要になるため、1回あたりの計算時間が長いほど、攻撃の成功に必要な時間も飛躍的に増大します。
前述のbcryptやArgon2は、このストレッチングの仕組みを組み込んで設計されており、計算コスト(繰り返し回数など)を調整できるため、将来的なコンピュータの性能向上にも対応しやすくなっています。
今すぐ確認!あなたのシステムは大丈夫?
開発者やシステム管理者の方は、自社で開発・運用しているシステムのデータベースを今すぐ確認してください。ユーザー認証に関わるテーブルで、パスワードがどのように保存されているでしょうか? もし、パスワードらしき文字列がそのまま読める状態で格納されていたら、それは一刻も早く対処すべき重大なセキュリティホールです。
もし平文で保存されていた場合の対応策は以下の通りです。
- 現状把握と計画策定: どのシステムで平文保存されているか、影響範囲はどれくらいかを正確に把握します。
- 移行方式の決定: ハッシュ化アルゴリズム(bcryptやArgon2を推奨)、ソルトの生成・保存方法を決定します。
- 移行実装: 既存ユーザーのパスワードを安全にハッシュ化+ソルト化する処理を実装します。一般的には、ユーザーが次回ログインした際に、入力されたパスワードを使って新しい方式でハッシュ値を生成し、古い平文パスワードを置き換える、といった段階的な移行が行われます。
- ユーザーへの告知とパスワード変更依頼: システム変更後、ユーザーにパスワードの再設定を依頼する必要があるかもしれません。その際は、理由を丁寧に説明し、協力を仰ぎましょう。
- セキュリティ専門家への相談: 不安な点や技術的に難しい点があれば、迷わずセキュリティ専門家に相談することを検討してください。
決して「今まで問題なかったから大丈夫」と考えないでください。事故は忘れた頃にやってきます。そして、その代償は計り知れません。
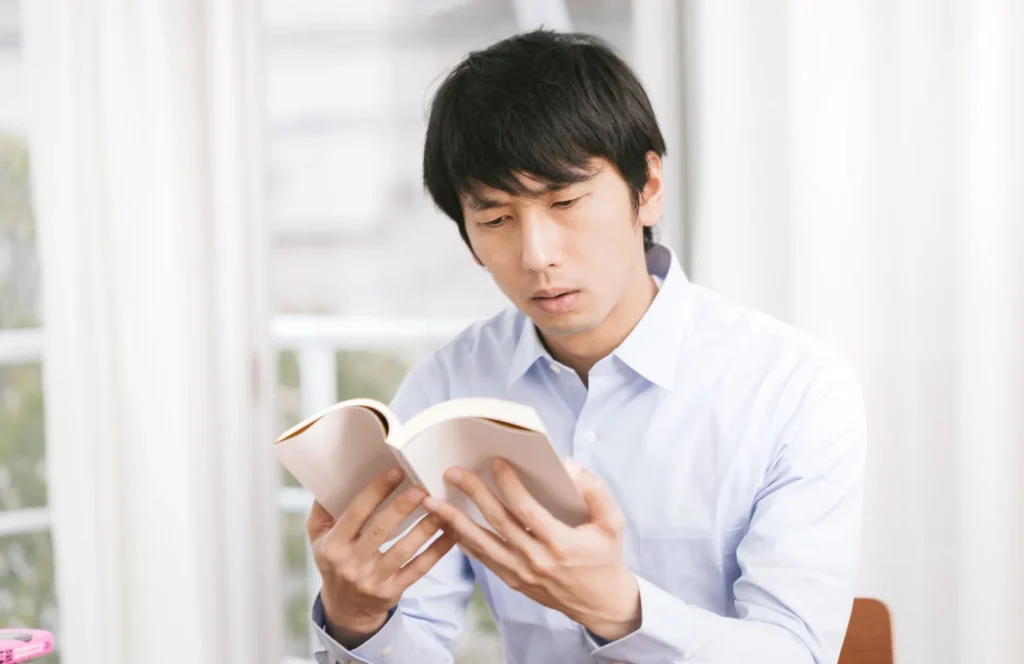
ユーザーとしてできること
システム側の対策はもちろん重要ですが、私たちユーザー自身がセキュリティ意識を高めることも不可欠です。
- パスワードの使い回しはやめる: サービスごとに異なる、推測されにくいパスワードを設定しましょう。
- 複雑で長いパスワードを設定する: 英大文字、小文字、数字、記号を組み合わせ、十分な長さ(最低でも12文字以上推奨)のパスワードにします。
- 二要素認証(2FA/MFA)を有効にする: 対応しているサービスでは、必ず二要素認証を設定しましょう。パスワードが漏洩した場合でも、不正ログインのリスクを大幅に低減できます。
- パスワードマネージャーを活用する: 複雑なパスワードを多数覚えておくのは困難です。パスワードマネージャーを使えば、安全にパスワードを生成・管理できます。

まとめ
パスワードを平文でデータベースに保存することは、情報漏洩時の被害拡大、パスワードリスト攻撃の助長、法令違反リスク、そして何よりもユーザーと自社の信頼を根底から揺るがす極めて危険な行為です。それはもはや「平成」の時代の遺物であり、令和のセキュリティ標準では到底許容されません。
安全なパスワード管理(ハッシュ化+ソルト+ストレッチング)は、もはや特別な対策ではなく、システム開発における「当たり前」の要件です。開発者やシステム管理者は、自社のシステムが適切にパスワードを保護しているか、定期的に確認し、必要であれば速やかに改善策を講じる責任があります。
利用者一人ひとりも、パスワードの使い回しをやめ、二要素認証を活用するなど、自衛策を講じることが重要です。
この記事をきっかけに、パスワード管理の重要性について再認識し、ご自身の関わるシステムや利用するサービスのセキュリティ向上に繋げていただければ幸いです。「まだ平成ですか?」と問われることのないよう、令和時代のスタンダードにアップデートしていきましょう。











