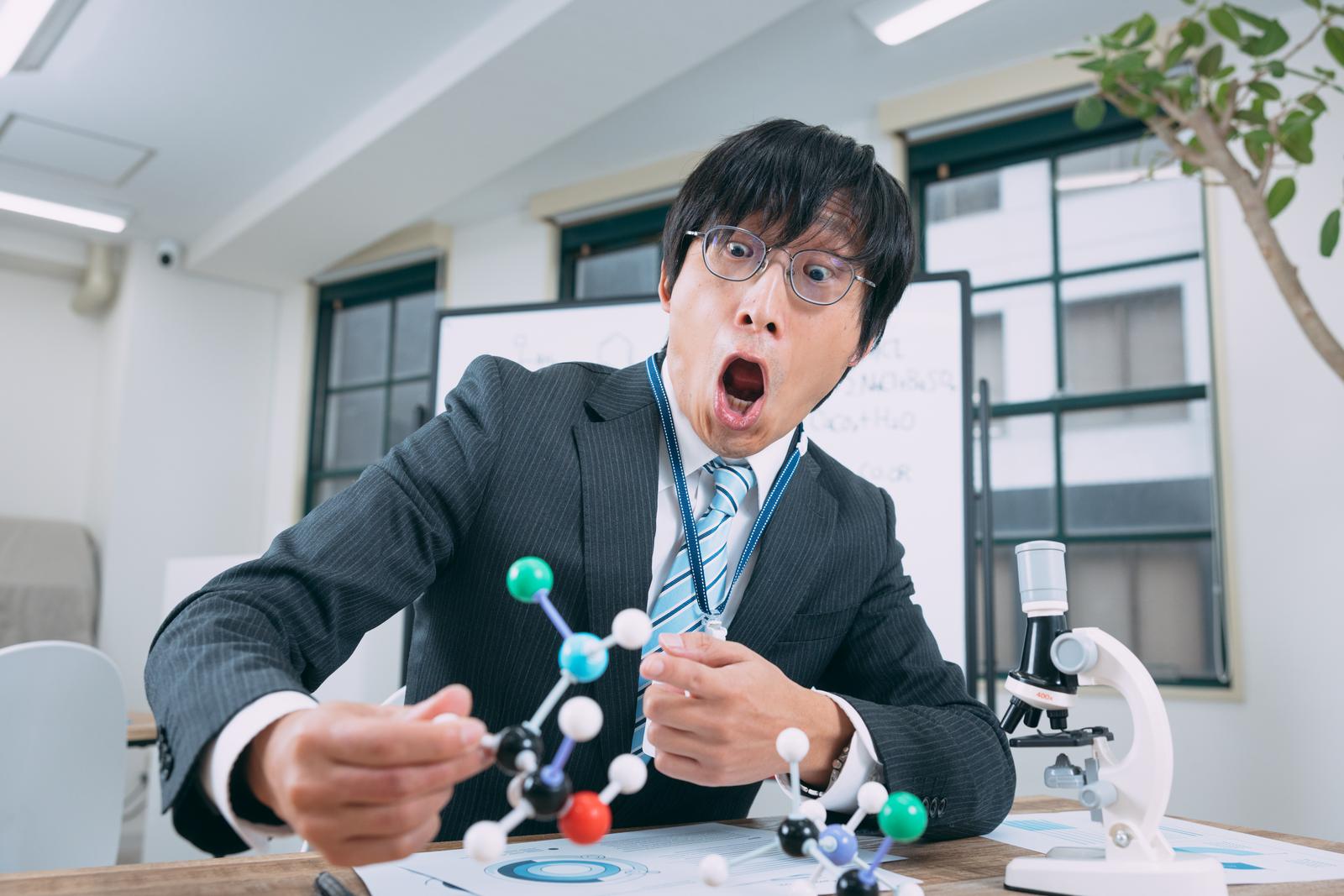こんばんは!IT業界で働くアライグマです!
「2025年の崖」—。この言葉を、あなたも一度は耳にしたことがあるかもしれません。経済産業省がDXレポートで警鐘を鳴らしたこの言葉は、一時期IT業界を席巻しましたが、最近では少しだけ下火になったようにも感じられます。もしかしたら、「コンサルタントが作り出した、ただの脅し文句だろう」と、どこか他人事に捉えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、断言します。「2025年の崖」は、今この瞬間も、すぐ足元で口を開けている極めて現実的な危機です。長年改修を繰り返してきた秘伝のタレのようなレガシーシステム、それを唯一理解していたベテランエンジニアの退職、そして、新しいビジネスの足かせとなる硬直化したIT基盤。
PjMとして多くの企業のシステムに触れてきた私から見れば、多くの組織がこの崖の淵を歩いているように見えます。この記事では、単なる脅威論を繰り返すのではなく、崖の正体が何であるかを解き明かし、PjMの視点から、どうすればこの崖から落ちずに済むのか、その現実的なプロジェクト推進術を解説していきます。
「2025年の崖」とは何か?単なる脅し文句ではない、その深刻な中身
まず、この言葉の原点と、その深刻さを正確に理解しましょう。これは、単なる未来予測ではなく、具体的なデータに基づいた警告です。
経済産業省が鳴らした警鐘
「2025年の崖」とは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」で初めて用いられた言葉です。レポートでは、もし日本企業が既存の複雑化・老朽化したレガシーシステムを刷新できなければ、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると指摘されました。これは、現在の日本の国家予算の約1割に匹敵する、驚くべき金額です。
なぜ、これほどの損失が生まれるのか。レポートは、その原因が、多くの企業が抱えるレガシーシステムにあると断じています。
なぜ今、問題なのか?レガシーシステムが抱える3つの時限爆弾
「うちは今のシステムで問題なく業務が回っているから大丈夫」—。そう考えるのは非常に危険です。レガシーシステムは、気づかぬうちに組織を蝕む、3つの時限爆弾を抱えています。
爆弾1:変更不能な「技術的負債」の塊
長年の改修を重ねた結果、多くのレガシーシステムは、もはや誰も全体像を把握できない「スパゲッティコード」の塊と化しています。ドキュメントは更新されず、テストコードも存在しない。一つの小さな機能修正が、どこに影響を及ぼすか予測できず、改修には莫大な時間とコストがかかります。これは、いわゆる「技術的負債」が限界まで膨れ上がった状態です。
こうした、テストコードもなくドキュメントも不十分なコードベースを、安全に、そして着実に改善していくための具体的な技術と思想を解説した名著があります。
この書籍は、振る舞いを維持したままコードを改善していくための具体的な手法がカタログ形式でまとめられています。巨大なコードベースを前に絶望しているチームにとって、まさに必読の一冊です。
爆弾2:ベテラン頼みの「属人化」とノウハウの喪失
これらの複雑なシステムを支えているのは、往々にして、そのシステムを長年守り続けてきた一握りのベテランエンジニアです。しかし、彼らの多くが2025年以降、定年退職の時期を迎えます。彼らが去った後、残されたブラックボックス化したシステムを、一体誰が保守・運用できるというのでしょうか。組織からのノウハウの喪失は、事業継続における致命的なリスクです。
爆弾3:DX時代における「ビジネスチャンス」の逸失
最も深刻なのが、この問題です。現代のビジネスは、クラウド、AI、IoT、モバイル対応といった新しいテクノロジーと密接に結びついています。しかし、硬直化したレガシーシステムは、これらの新しい技術との連携を著しく困難にします。競合他社がデータを活用した新しいサービスを次々と生み出す中で、自社だけが時代遅れのシステムに足を引っ張られ、決定的なビジネスチャンスを逃し続けることになるのです。
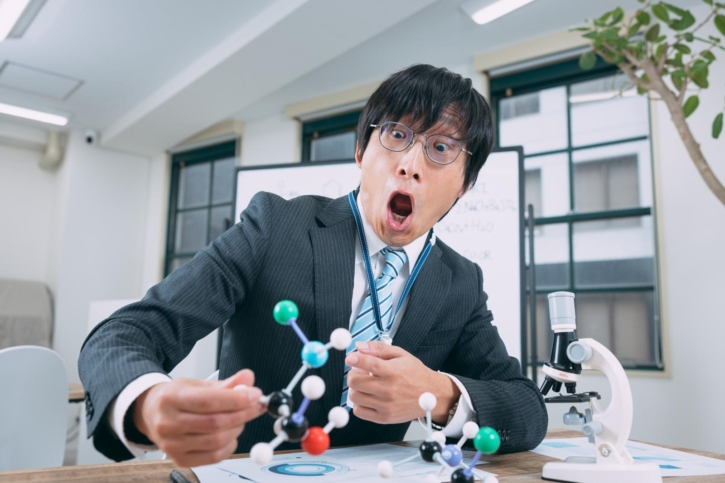
PjMが見た、レガシー刷新プロジェクトが失敗する典型パターン
「危機は分かった。だから、うちも刷新プロジェクトを立ち上げた」という企業も多いでしょう。しかし、残念ながら、その多くが失敗に終わるか、塩漬けになっているのが現実です。PjMとして、私が目撃してきた失敗の典型パターンを3つご紹介します。
パターン1:「ビッグバン」アプローチの罠
最も多い失敗が、既存のシステムを一度に全て新しいものに置き換えようとする「ビッグバン」アプローチです。これは、数年がかりの超大規模プロジェクトとなり、要件定義だけで1年以上かかることも珍しくありません。しかし、その間にビジネス環境は変わり、新しい要求が次々と生まれます。結果として、プロジェクトは永遠に終わらず、完成した頃には時代遅れのシステムが出来上がるという悲劇を迎えます。
パターン2:経営層の無理解と「IT部門への丸投げ」
レガシー刷新は、単なるITの問題ではありません。業務プロセス、組織のあり方、そしてビジネスモデルそのものを見直す「経営課題」です。にもかかわらず、多くの経営層はこれを「古くなったシステムの入れ替え」としか捉えず、「あとはIT部門でよろしく」と丸投げしてしまいます。明確な経営戦略とトップの強いコミットメントがなければ、部門間の調整は進まず、プロジェクトは必ず頓挫します。
パターン3:現場の抵抗と「今のままでいい」という幻想
意外なようですが、刷新プロジェクトの最大の敵は、しばしば「現場の利用者」となります。長年慣れ親しんだ(たとえ非効率であっても)業務フローや画面操作が変わることに、人間は本能的な抵抗を示します。「新しいシステムは使いにくい」「前のやり方の方が良かった」という声が、プロジェクトの推進力を削いでいくのです。

崖から落ちないための現実的プロジェクト推進術
では、どうすればこの困難なプロジェクトを成功に導けるのでしょうか。PjMとして私が最も重要だと考える、3つの現実的な推進術を提案します。
推進術1:モノリスからマイクロサービスへ、段階的な移行計画
一度に全てを捨て去る「ビッグバン」ではなく、段階的に、一つ一つの機能を新しいシステムに切り出していくアプローチを取るべきです。例えば、巨大な一枚岩(モノリス)であるレガシーシステムの中から、まずは「顧客管理」の機能だけを独立したサービス(マイクロサービス)として切り出し、新しいシステムを構築する。そして、古いシステムの顧客管理機能を、新しいサービスを呼び出す形に置き換えるのです。この「ストラングラー(絞め殺し)パターン」と呼ばれる手法を繰り返すことで、リスクを最小限に抑えながら、着実にシステムを近代化していくことができます。
そして、この新しいサービスをどう設計していくべきか、その強力な指針となる設計思想が「ドメイン駆動設計(DDD)」です。
この書籍は、複雑な業務ロジックをいかにしてシンプルで堅牢な設計に落とし込むかを解説しています。レガシーシステム刷新という、まさに複雑なドメインに立ち向かう上で、強力な武器となるでしょう。
推進術2:ROIを明確にし、経営層を「仲間」にする
経営層を動かすのは、技術の素晴らしさではなく、「それがどれだけビジネスに貢献するのか」という一点に尽きます。「サーバーコストがこれだけ削減できます」「この改修により、新商品の開発期間が半年短縮できます」といった、具体的な投資対効果(ROI)を、数字で示すことが不可欠です。レガシー刷新を「コスト」ではなく「未来への投資」として認識させ、経営層をプロジェクトの最大の「仲間」にするのです。
推進術3:現場を巻き込み、小さな成功を積み重ねる
現場の抵抗を乗り越える唯一の方法は、彼らをプロジェクトの当事者として巻き込むことです。アジャイル開発の手法を取り入れ、短いサイクルでプロトタイプを開発し、実際に触ってもらいながらフィードバックを得る。そして、「この機能は便利になった」「この改善で残業が減った」といった「小さな成功」を意図的に作り出し、それを全部門に共有するのです。小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きな変革への推進力となります。

まとめ
「2025年の崖」は、決して遠い未来の話でも、他人事でもありません。それは、多くの企業が抱える「技術的負債」という名の時限爆弾が、いよいよ爆発寸前にあるという、現実の危機です。
しかし、これは単なる危機ではなく、組織が生まれ変わるための、またとない「機会」でもあります。硬直化した業務プロセスを見直し、データを活用できる基盤を整え、新しいビジネスモデルへと舵を切る。レガシーシステムの刷新は、そのための痛みを伴う、しかし避けては通れない外科手術なのです。
この困難な手術を執刀できるのは、技術とビジネスの両方を理解し、組織を動かす力を持った、私たちPjMやエンジニアしかいません。崖の淵で立ちすくむのか、それとも未来への懸け橋を架けるのか。今、私たちの真価が問われています。